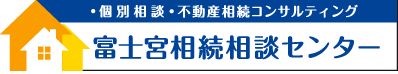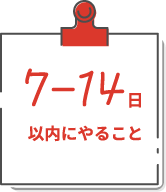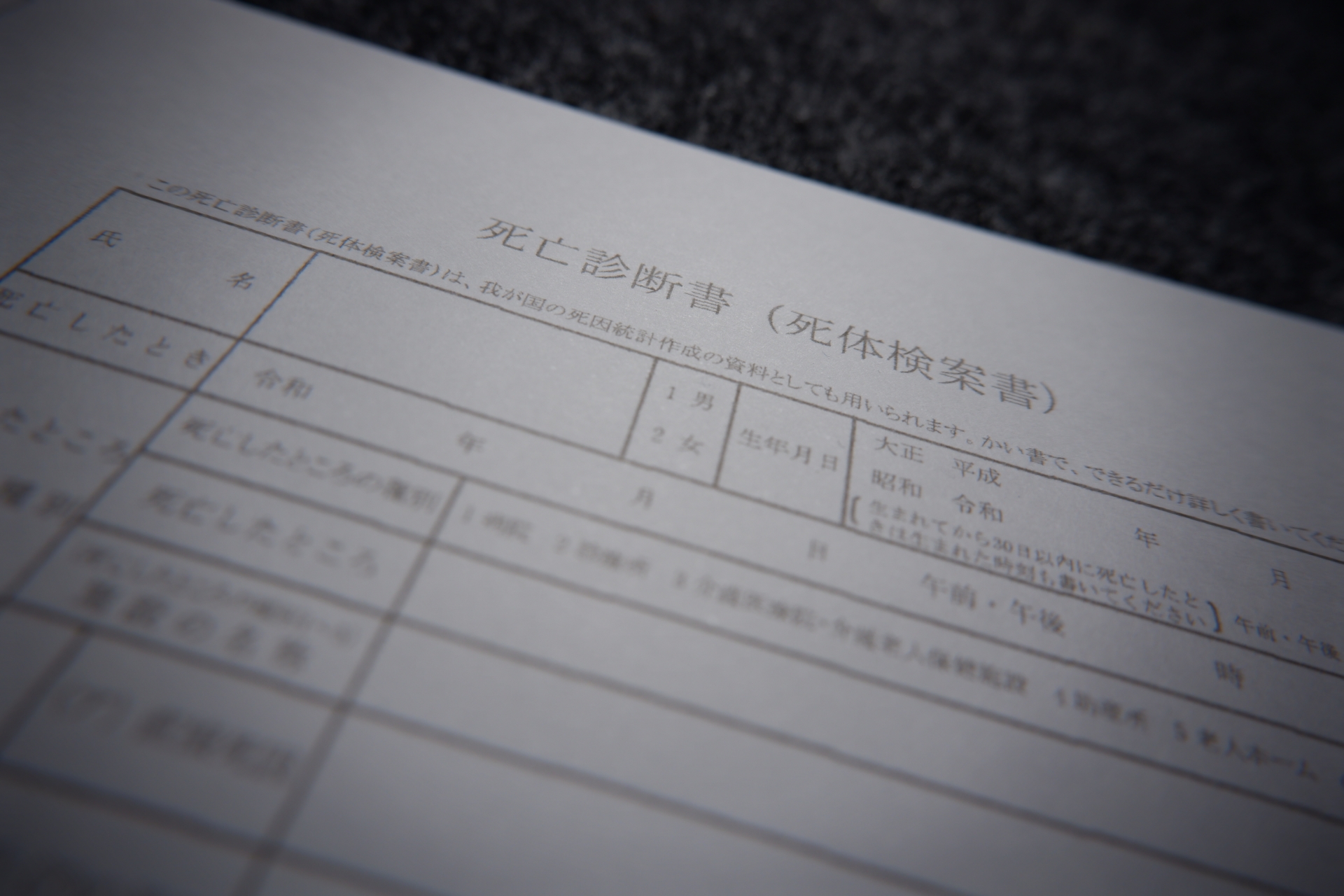相続の流れと手続き内容
7~14日以内にやること
死亡診断書・死体検案書の受け取り
死亡届の提出
死亡届は、死亡診断書又は死体検案書と一緒に渡されます。必要事項を記入後、以下の市町村役場へ7 日以内に提出します。
■死亡者の本籍地
■死亡地
■届出人の所在地
聖苑使用許可申請の提出
富士宮市の場合、死亡届を提出すると同時に聖苑使用許可申請を行い、使用許可証の交付を受けます。詳細は市役所に確認してください。
世帯主の変更
世帯主が亡くなった場合、14 日以内に『世帯主変更届』を市役所に提出します。
次の世帯主が明白であるときは世帯主変更届の提出は必要ありません。
国民年金・厚生年金の受給停止の手続き
年金を受給していた方が亡くなったら、年金事務所に『受給権者死亡届』を提出します。
■国民年金の手続き…14 日以内
■厚生年金の手続き…10 日以内
※亡くなった方が日本年金機構に個人番号(マイナンバー)の登録をしている場合は原則として『受給権者死亡届』の手続きを省略できます。
国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の喪失の手続き
国民健康保険加入者・後期高齢者医療保険加入者・介護保険加入者が亡くなった場合は14日以内に喪失手続きと保険証の返却が必要となります。
3~4カ月以内にやること
相続放棄・単純承認・限定承認の決定
資産相続には3つの方法があります。
■相続放棄:相続に関する権利を一切放棄すること
■単純承認:亡くなった人の財産をすべて相続すること
■限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐこと
相続放棄と限定承認の決定は、死亡日又は相続開始を知った日から3ヵ月以内に行う必要があり、家庭裁判所にて手続きを行います。尚、限定承認は相続人全員の同意が必要となります。
何もせずに3ヵ月経過した場合は、単純承認となります。
準確定申告
準確定申告とは、亡くなった人の確定申告を家族が代わりに行うことです。
準確定申告が必要になる方は、自営業だった方や不動産による家賃収入がある方などです。
準確定申告の期限は亡くなった日から4 か月以内です。
1年以内にやること
相続税の申告
相続税の申告期限は、死亡日又は相続開始を知った日から10 か月以内です。相続税の申告には、相続人や相続財産の確定、各相続人の納税金額の算出が必要となります。
相続税の申告が必要とされる場合でも、特例の適用により相続税がかからないケースもあります。
相続税の申告や相続税の特例などの利用は、相続人である納税者が自ら行わなければなりませんので難しいと感じたら線もウンカに相談することをお勧めします。
遺留分侵害額の請求
遺留分侵害額の請求とは、法定相続人が最低限取得できる一定割合の相続財産を主張する
権利を指します。
遺言によって相続財産が法定相続人ではなく他人へ相続されると、法定相続人は相続財産を一切受け取ることができません。
このような場合、法定相続人は遺留分を侵害している人に対して、最低限取得できる一定割合の相続財産について遺留分侵害額の請求ができます。
期限は、死亡日または相続開始を知った日から1 年以内です。
なるべく早めにすること
相続人や相続財産の確定
亡くなった方の財産を相続できる方を法定相続人といい、法定相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡するまでの戸籍謄本を確認します。
相続財産の対象となるもの
プラス財産…現金・預貯金・不動産・株式・車・美術品など
マイナス財産…借金・ローンなど
遺産分割協議・遺産協議書の作成
法定相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議とは、遺言がない場合や、遺言以外の内容で遺産を分割する際に誰が何をどれだけ相続するかを決める話し合いのことです。遺産分割協議は相続人全員で行います。内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
相続財産の名義変更など
遺産分割協議書が作成できたら、相続人は預貯金や不動産の名義変更、相続財産の換金を行います。
預貯金の名義変更は、相続人本人が必要書類を用意し銀行で手続きします。
不動産の名義変更は、一般的に司法書士に依頼します。
富士宮相続相談センターが
選ばれる4つの理由

1つの窓口で
手続きが完結します
幅広い分野におよぶ相続の手続きについて、当センターが窓口となり税理士・司法書士・弁護士など士業の先生と連携をしてサポートいたします。

部分的な解決ではなく、
総合的な解決策を見出します
ご相談者様の立場で、どうすることが最善なのか?部分的な解決ではなく、総合的な視点で手続きを進めていきます。

分けるのが難しい資産
「不動産」の専門家です
相続で揉める原因になることが多い不動産について、遺産分割から相続手続き後の活用や売却まで一貫してサポートいたします。

相談場所・相談方法も
柔軟に対応いたします
市役所から徒歩1分の事務所での相談が基本になりますが、事情によってはご自宅やZOOMでの相談など柔軟に対応いたします。